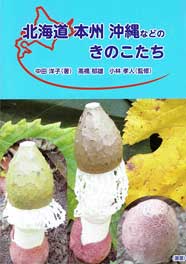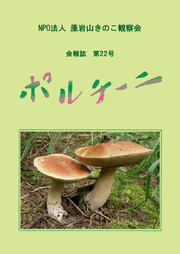【新年あけまして おめでとうございます!!】
本年も会員の皆様と地域住民の方々と共に、きのこを楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆ STV札幌ふるさと再発見2024/9/14にて ◆
◆ 当会が放映されました! ◆
本年も会員の皆様と地域住民の方々と共に、きのこを楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆ 当会が放映されました! ◆
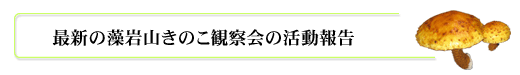
2025年10月30日(木)どさんこワイドお絵かきですよ!に出演
2025.11.01
どさんこワイドのデレクターさんから「急なお願いで大変申し訳ないですが、30日夕方に行っている「お絵描きですよ!」に出ていただきたいと思いますが・・・」と、困っているご様子でのお電話が入りました。明々後日に膝の手術を控えておりましたが、私ども当団体のPRにもなりますし、また、STVさんには大変お世話になっておりますので、急遽な事でしたが、何とかしたいと思いまして、当会員の数人にお電話をしての出演依頼をしましたところ、2名の方が快く対応して下さいました。
病室から心配しながらテレビを見ておりましたが、お二人が笑顔で元気よく「きのこウイークですよ!オー!!」で登場したお姿に涙が出ました。
若生敏子さんは、当団体の黄色いジャンパーを身に着けてベニテングタケとタマゴタケの解説がとても上手で良かったです。江川俊子さんのお絵描きは上手で分かり易くてとても良かったです。最後の「点々・・・・」のペンの運……続きを読む
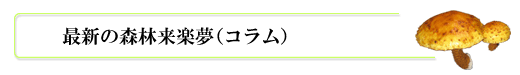
2025年11月2日(日)エノキ採りIN新篠津実施報告
2025.11.03
札幌は曇りでしたが、新篠津方面は小雨、新篠津道の駅駐車場になんと8名が集合しました。エノキタケの魅力か、集合場所が良かったのか、思った以上の参加者でした。最初に10分ほど、自己紹介・近況報告やM班長持参のキノコで勉強会をやりました。 現場まで車で10分ぐらい、5台が1列になって移動、心配していましたが無事到着。前日の雨で発生状況がよさそうと思い、キノコ探しへ。2日前の下見で手前の方は人が入り無かったので、車で移動し奥の方から入りました。
草をかき分け10mも進むと、木のある所はなんと水浸し、石狩川が氾濫してあたりは一面泥水だらけ・・・・・・。水の無い高い場所をあちこち探したが、ダメでした。ヌメリスギタケモドキ、ムラサキシメジ、ツチスギタケ、チャワンタケが見られた。1週間後に再度チャレンジすることにして、早めに解散。 (記:松原 写真:池ノ谷)

陸上に植物が存在したのは約4億年前といわれています。そこは赤茶けた乾燥した大地であり重力に逆らって養分と水分の補給のために植物は菌の助けを借りて陸上に進出し巨大化されました。
やがて植物は森をつくるようになり、森林は幹や枝など多量の有機物を生み出すのですが、生み出された有機物を効率よく分解する担当者はまだ出現していきせんでした。1億年から2億年前に,森林の有機物を効率よく分解するサルノコシカケやオチバタケ等のきのこが地球上に出現したといわれております。
また、ブナやマツの仲間と外生菌根をつくって共生するイグチ類、テングタケ類等は共生菌として地球に出現したのも1億年くらい前だろうといわれており、その後現在でも陸上植物のほとんどは菌類と共生し、栄養のやり取りをして生きております。
きのこは森の中で誕生した。
そして森はきのこなしでは生きていけない。
森へ行けばいろんな色と形のきのこと出会う。
森で生まれ、世界の森をつくったきのこを愛し、きのこの生活環境を守るうえでも当団体は、植樹やその後の森の育成として枝切り・下草刈等、またゴミ拾いを環境保全活動として継続実践して参ります。
「山があるから山登りをする」「森にきのこがあるからきのこ採りをする」のは、人として自然体です。雪が解け春になると森へ行き、四季折々自然のお恵みをいただく楽しみをもって人生を生きることは、潤いのある素敵なことす。でもそれが命とりになったり、食中毒にかからないで、きのこを美味しく食していただきたいものです。
地域住民の皆さんに、きのこを安心安全に美味しく食していただきたく、当団体は菌類の普及啓発活動を継続実践して参ります。また、小学生などの環境教育として、きのこ、樹木、植物の環境学習として学習のお手伝いをもボランティアで行っております。
やがて植物は森をつくるようになり、森林は幹や枝など多量の有機物を生み出すのですが、生み出された有機物を効率よく分解する担当者はまだ出現していきせんでした。1億年から2億年前に,森林の有機物を効率よく分解するサルノコシカケやオチバタケ等のきのこが地球上に出現したといわれております。
また、ブナやマツの仲間と外生菌根をつくって共生するイグチ類、テングタケ類等は共生菌として地球に出現したのも1億年くらい前だろうといわれており、その後現在でも陸上植物のほとんどは菌類と共生し、栄養のやり取りをして生きております。
きのこは森の中で誕生した。
そして森はきのこなしでは生きていけない。
森へ行けばいろんな色と形のきのこと出会う。
森で生まれ、世界の森をつくったきのこを愛し、きのこの生活環境を守るうえでも当団体は、植樹やその後の森の育成として枝切り・下草刈等、またゴミ拾いを環境保全活動として継続実践して参ります。
「山があるから山登りをする」「森にきのこがあるからきのこ採りをする」のは、人として自然体です。雪が解け春になると森へ行き、四季折々自然のお恵みをいただく楽しみをもって人生を生きることは、潤いのある素敵なことす。でもそれが命とりになったり、食中毒にかからないで、きのこを美味しく食していただきたいものです。
地域住民の皆さんに、きのこを安心安全に美味しく食していただきたく、当団体は菌類の普及啓発活動を継続実践して参ります。また、小学生などの環境教育として、きのこ、樹木、植物の環境学習として学習のお手伝いをもボランティアで行っております。

NPO法人 藻岩山きのこ観察会
代表 中田洋子
〒064-0944
北海道札幌市中央区円山西町8丁目5番1
ピアリッチ202号 中田洋子宅内
Tel・Fax 011-631-8344
携帯電話 090-5222-5716
メール nakata.03-m.k.k@jcom.home.ne.jp
現在会員数(家族会員含め)250名
代表 中田洋子
〒064-0944
北海道札幌市中央区円山西町8丁目5番1
ピアリッチ202号 中田洋子宅内
Tel・Fax 011-631-8344
携帯電話 090-5222-5716
メール nakata.03-m.k.k@jcom.home.ne.jp
現在会員数(家族会員含め)250名
『藻岩山きのこ観察会は、主に藻岩山、旭山の自然を楽しみながら、きのこを通して会員の交流を図り、現状の植生環境に十分注意を払い、菌類の発生状況や役割に関する観察、記録、標本づくりなどを行い、その資料を地域社会に貢献できるようにし、さらに菌類の啓発・普及活動と環境保全活動を行うことを目的としています。』